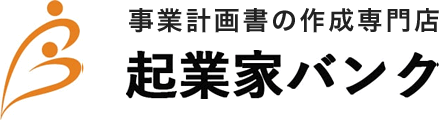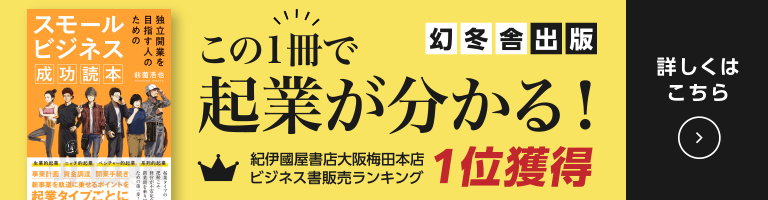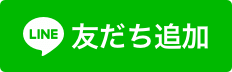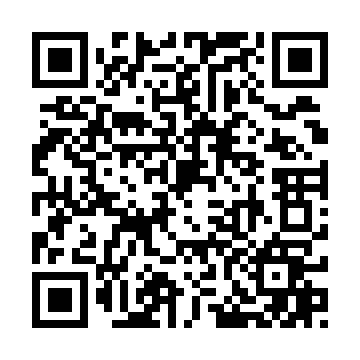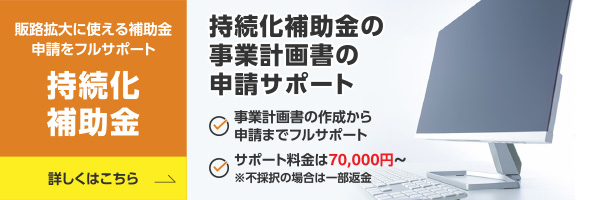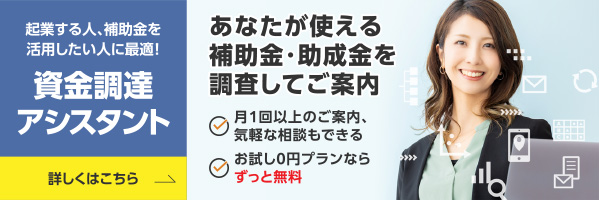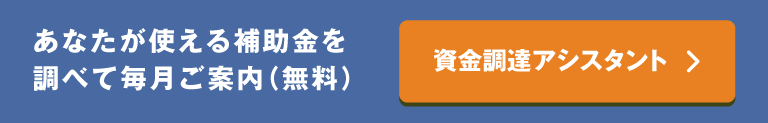小規模事業者持続化補助金でホームページ制作費を節約

スマートフォンひとつで簡単にインターネットにアクセスできる現代では、商品を購入したりサービスを受けたりする前に、企業の評判や信頼性をネットで確認するのが当たり前になっています。そのため、企業にとってホームページは名刺以上に重要な存在となっており、逆にホームページがないと、お客様に不安を与えてしまいます。
しかし、ホームページの制作には、意外と費用もかかります。「コストが心配で手が出せない」という小規模事業者の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ホームページの制作費用を大幅にカバーできる【小規模事業者持続化補助金】についてご紹介します。賢く活用すれば、自己負担を抑えてプロ品質の集客ツールを手に入れることも可能です。ぜひ最後までチェックしてみてください!
ホームページ制作費も補助対象になる
小規模事業者持続化補助金では、「ウェブサイト関連費」として、ホームページ制作やECサイト構築などの費用が補助金の対象となります。ただし注意点として、単なる名刺代わりのホームページや情報掲載だけの簡易サイトだと、対象外と判断される可能性もあります。採択されるには、集客や販路拡大といった明確なビジネス目的があることが重要です。
補助金の対象となる具体的な制作例は次のとおりです。
企業の紹介ページ
会社概要、事業内容、スタッフ紹介、アクセス情報などを掲載したサイト
ネットショップ
商品販売機能や、オンラインで予約・決済ができるシステムを含むサイト
ランディングページ(LP)
特定商品やサービスに特化したキャンペーン用のサイト
スマホ対応のレスポンシブサイト
PC・スマホ・タブレットなど様々な端末に最適化された見やすいサイト
補助される金額
補助率: 制作費の3分の2(原則)
上限額: 50万円~200万円
ウェブサイト関連費の上限: 全体の25%
たとえば、補助額が50万円の場合、ウェブサイト関連費として認められるのは、最大12.5万円(=50万円×25%)となります。補助額が200万円の場合は、その25%の50万円となります。
つまり、ホームページ制作費は補助対象になるものの、全体の補助金の中で使える割合には上限が定められていることを、あらかじめ理解しておきましょう。
ホームページ制作費を節約するポイント
小規模事業者持続化補助金は、ホームページ制作費も補助対象となりますが、補助金全体のうち最大で25%までという制限があります。つまり、希望するホームページを作りたくても、補助金だけでは足りない可能性が高いのです。
そこで、自己負担を最小限に抑えながら、希望するホームページを制作するための工夫をご紹介します。
明確な目的とターゲットを設定
まず、誰に、どんな価値を届けたいのかを明確にすることが重要です。例えば、「地域の主婦層向けに健康志向のお惣菜を販売するネットショップ」など、ターゲット像と訴求ポイントを具体化すれば、必要なページ構成やコンテンツが明確になり、不要なデザインや機能に費用をかけずに済みます。明確なターゲット設定は、補助金の採択率向上にもつながります。
テンプレート型の制作会社を活用
テンプレートのデザインが豊富であれば、一から作り上げるものと変わらない完成度の高いホームページを作ることができます。リーズナブルな価格で、必要なページ構成(トップページ・会社紹介・お問い合わせフォームなど)を備えたサイトを制作でき、十分に集客効果を発揮できるホームページが手に入ります。
分割払いを活用する
補助金には「事業実施期間」というものがあり、その期間内に完了した制作費用のみが補助対象となります。そのため、事業実施期間内に、ホームページの基本構成や必要最低限の機能を完成させ、その後、分割払いを活用して、追加の機能やデザインを少しずつブラッシュアップしていくという進め方も好まれています。この方法なら、限られた補助金枠を最大限活用しながら、自己負担を抑えて、クオリティの高いホームページを段階的に仕上げることができます。
補助金採択の鍵を握る「事業計画書」の書き方
小規模事業者持続化補助金の採択において、最も重要なのが、経営計画書兼補助事業計画書(様式2)の内容です。書類の出来が、審査結果に直結すると言っても過言ではありません。審査員が「この事業に補助金を出す価値がある」と納得できる内容を作り込む必要があります。
計画書は単に事実を並べるのではなく、「課題→戦略→実施内容→成果」という一貫したストーリーを持ち、データや客観的な根拠を交えて説得力を高めましょう。さらに、自社の強みや地域特性を盛り込むことで、他の申請者との差別化を図ることができます。
経営計画書の書き方
経営革新書では、現在の経営状況をふまえて、どんな課題を抱えており、今後どう成長させていくのかを記載します。特に、以下の3点を押さえることが重要です。
自社の現状と課題
この項目では、現在の事業の状況や直面している経営課題を具体的に記載します。売上の推移、顧客の動向、コロナや物価高などの外的要因の影響などを数値や事実に基づいて説明しましょう。
【記載例】
当店は地域密着型の整体院として、地元の高齢者層を中心に長年営業してきましたが、コロナ禍以降、来院数が減少し、新規顧客の獲得が課題となっています。紹介による集客が中心であり、ネット上での情報発信や予約機能が整っていないため、Webからの新規獲得がほとんどないのが現状です。
顧客ターゲットと市場環境
ここでは、対象とする顧客層やそのニーズ、また周辺の競合状況、市場トレンドなどを分析し、自社がどのようなポジションにあるかを示します。できれば第三者データ(統計や調査レポート)も活用して、客観性を持たせましょう。
【記載例】
近年では、30〜40代の働く女性層が健康維持のために整体を利用するケースが増えており、特にスマートフォンでの検索・予約が主流となっています。当店周辺にも複数の新規サロンが開業しており、Web対策を強化することが競争力の確保に不可欠です。
経営方針と今後の展開
この部分では、今後の経営の方向性と、それを実現するための具体的な方策を記載します。経営課題をどのように克服し、どのように売上や集客を伸ばしていくかを明確にし、それにホームページがどう寄与するかを説明します。
【記載例】
今後は、これまで接点のなかったスマホ利用者層を新たなターゲットとし、予約の利便性や情報発信を強化するため、ホームページを新規構築します。店舗の紹介やスタッフの紹介ページに加え、オンライン予約機能やお客様の声などを充実させることで、信頼性を高め、新規来院数の増加を図ります。
補助事業計画書の書き方
補助事業計画書では、実際に補助金を使って行う事業について、目的・内容・期待される成果・実施体制を具体的に記載しましょう。ストーリー性と具体性を持った事業計画書を作成することで、採択の可能性がぐっと高まります。ぜひ、補助金の目的と事業の実現性がしっかり結びついた説得力のある計画を目指しましょう。
ホームページ制作の目的
まず、補助事業を行う目的を明確にしましょう。単に「ホームページを作る」では不十分で、「なぜ必要なのか」「どのような効果が見込まれるのか」を、課題とのつながりを意識して記載することが重要です。
【記載例】
Web上での情報発信力を高め、新規顧客の獲得を目的としてホームページを制作します。具体的には、スマートフォン対応のレスポンシブデザインを採用し、24時間予約受付、サービス紹介、よくある質問ページを通じて、ユーザーの不安を解消し、来店意欲を高めます。
制作内容と構成
実施する内容は、なるべく具体的に記載しましょう。「どのようなページを作るのか」「どんな機能があるのか」を明記することで、審査員の理解が深まり、現実的な計画であると判断されやすくなります。
【記載例】
構成はトップページ、サービス紹介、価格表、よくある質問、お客様の声、アクセス情報、予約フォームなどです。WordPressを使用し、ブログ更新機能も設けて定期的な情報発信が可能な設計とします。
期待される成果
補助金の目的が「販路開拓」や「売上向上」であることから、成果目標はできるだけ数値で示すことが重要です。「どのくらいの効果が見込まれるのか」を明確に記載します。
【記載例】
公開から3ヶ月以内に月間アクセス数を500件以上に増加させ、予約件数を月30件まで引き上げることを目指します。既存顧客への再訪率も改善し、年間売上を20%増加させる見込みです。
実施スケジュールと体制
補助金申請書には、事業の実施スケジュールと、その実行体制(誰が何を担当するか)も求められます。無理のない現実的な工程であることを示し、体制の信頼性をアピールしましょう。
【記載例】
6月中に制作会社を選定し、7月に制作開始します。9月中旬までに公開を予定し、代表者が進行管理を行い、原稿作成や内容確認は従業員が分担する体制で実施します。
採択率を高めるためにできる3つのこと
補助金申請の最大のハードルは、「採択されるかどうか」です。いくら優れた取り組みでも、書類の内容が不十分だと不採択になる可能性があります。そこで、採択率を少しでも高めるために、事前にできる簡単な工夫をご紹介します。
商工会・商工会議所のサポートを活用する
補助金の申請を検討している方は、まず地元の商工会や商工会議所に相談するのがおすすめです。申請前に無料でアドバイスを受けられるだけでなく、過去に採択実績のある担当者から直接フィードバックをもらえることもあります。
書類の添削や内容のブラッシュアップに加え、提出までのスケジュール管理の支援など、実務的なフォローもしてもらえるため、初めての申請でも安心して進めることができます。
採択事例を研究する
申請書の構成や表現に悩んだら、過去の採択事例を参考にするのが効果的です。中小企業庁が運営する「ミラサポplus」では、実際に採択された申請書の一部が公開されており、同業種・類似の取り組みを参照することで、自分の計画書にどのような工夫を加えるべきかが見えてきます。
特に、表現の仕方や数字の使い方、事業の必然性の伝え方など、成功例から学べるポイントは多いです。
専門家にサポートを依頼する
「時間がない」「文章に自信がない」「確実に採択されたい」という方は、行政書士や中小企業診断士などの専門家に相談・依頼するのも一つの方法です。
費用は発生しますが、書類作成にかかる手間を省けるだけでなく、専門家の目線から申請書の改善ポイントを的確に指摘してもらえるため、採択率の向上が期待できます。また、補助金に詳しい専門家は最新の審査傾向にも通じているため、戦略的な書き方をサポートしてくれます。
まとめ
小規模事業者持続化補助金を活用すれば、ホームページ制作費の一部を補助金でまかなうことができます。ただし、ウェブ関連費は補助金額の最大25%までという制限があるため、費用を抑える工夫や計画が必要です。
補助金の採択を目指すには、事業計画書の質がカギとなります。「誰に・何を・どう届けるか」を明確にし、説得力のある構成で書類を作成しましょう。さらに、商工会議所・商工会への相談や採択事例の研究、専門家のサポートも有効です。限られた資源を有効活用し、ホームページを通じてビジネスの成長につなげていきましょう!
今回はここまで。
お役に立てたでしょうか?
起業、融資、補助金などについて知りたいことがあれば、公式LINEからお尋ねください。匿名でのご相談にも広く対応しています。営業や勧誘は一切行いませんので、お気軽にお問い合わせください。
公式LINE:友達登録
https://page.line.me/vwf5319u